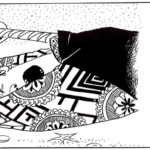芸術は高尚である。
しかし、高尚であればあるほど、ふつうの人にはわかりにくい。
芸術家は、だれしも高尚な作品を創りたい。だが、その才能がないとき、芸術家は往々にして、単にわかりにくい作品を創る。それをありがたがる人間がいるから、エセ芸術家が世にはびこる。
“芸術家”は、多くの人にとって憧れの職業ではないだろうか。私も若いころは、「ゲイジュツカ」という響きに魅了された。己の才能に恃み、美の本質に向き合い、歴史に残る作品を創造すべく、日々、苦悩する。“生活”などという俗事から離れ、崇高で、優雅で、充実した人生を送る。
水木サンは戦後の一時期、無職に近い生活をしていた。戦争で片腕を失い、「小便をするような感じで人が死んでいく」(京極夏彦氏から聞いた水木語録。「茂鐵新報」通巻1-18号にも掲載)戦場から帰還して、現実生活になじめなかったからだろう。
水木サンらしき青年が駅前にぼんやりと佇んでいると、長時間、落ちている切符をさがしている男に出会う。熊谷という詩人で、無一文で暮らしながら、『食うために働くのはバカバカしいですからねえ』とうそぶく。青年は、『全く私と同じ意見ですねえ』と意気投合し、熊谷の住む掘っ立て小屋に転がり込む。
そこで大鍋の雑炊を供されるが、中身は八百屋でもらった野菜くずや、桶いっぱい5円で買った魚のハラワタや頭である。水木青年があきれると、熊谷は悪びれることなく、『人の捨てるものには栄養もありますし』と、にんまり笑う。
そして、『働くことなく毎日上野の図書館にかよい、詩の研究に没頭しています』とまじめに語り、『芸術家にとっては理想的な生活じゃありませんか』と、水木青年を感心させる。
熊谷は立ち退きを迫られており、近々、数人の芸術家仲間と浅草の焼けビルを不法占拠する予定だと告げる。水木青年もこの行動に加わり、東京都と交渉の結果、焼けビルではなく、月島にある引き揚げ者の寮の一室を獲得する。
集まった面々を見て、熊谷は、『これから日本を背負って立つ詩人、芸術家が集まったわけだが』と豪語するが、全員無職で、生活費のアテがない。水木青年が、『普通に働いたら』と提案すると、熊谷はこう答える。
「普通に働くぐらいなら、誰だって詩人になりゃしねぇよ」
それに対し、『オ○○コ詩人』(1日たりとも女なしではいられない)が応じる。
「ほんとだ。芸術の時間、すなわちなまける時間がほしくてみんな芸術家になったんだ」
熊谷が、『お前、そんな正直なことをいうもんじゃないよ』とたしなめたあと、冒頭の一言をのたまう。このあたりの水木サンの冴え具合には、ほとほと感心させられる。そうか、芸術家に憧れていたオレは、実はなまける時間がほしかっただけなのかと、厳然たる事実を突きつけられる思いだ。
“才能”という影も形もない存在を前面に押し立て、世の中の役にも立たない“作品”を垂れ流す“芸術家”や“表現者”は、世にあふれている。平和で自由で豊かな日本ならではだろう。彼らが世の中をナメておれるのは、『ウドンのような字』を、芸術と評価する人間がいるからだ。実にありがたいことである。
こんな芸術家集団に紛れ込んだ水木青年はどうなったか。
彼らは一致団結して、配給の魚屋をやることで盛り上がるが、片腕のため唯一反対した水木青年にすべてを押しつけ、遁走したり、酔いつぶれたりして、いっこうに働かない。挙げ句の果てに、町内の女性の処女膜を破って、怒った被害者の兄に、無関係の水木青年が殴られる。
水木青年が、『俺、今日でやめさせてもらうぜ』と言うと、『ニセ芸術家、馬脚をあらわしたな』と怒鳴られ、石を投げて追いかけてくるのを、命からがらかちどき橋を渡って築地まで逃げ延びるのである。
似たような話は、水木サンの回想録にも何度か出てくるので、実体験が元になっているのだろう。マンガの最後はこう結ばれる。
『それは思い出すたびにおそろしき芸術家の群れだった』
(「街の詩人たち」より)