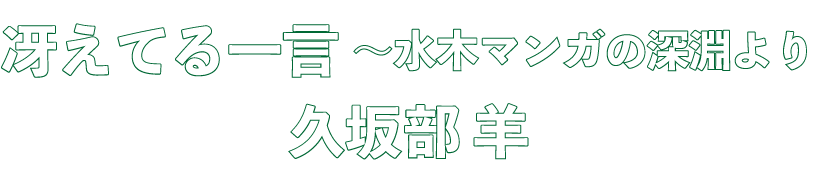新型コロナウイルスが蔓延し、緊急事態宣言が広まって経済が混乱したとき、文化の存続を訴える声があちこちから聞こえた。劇場や美術館や書店など、文化が稼ぐ舞台が閉鎖されて、収入が激減したからだ。文化を守ろうという動きの根本は、文化が重要であるという認識だろう。
東日本大震災をはじめとする大災害のときにも、文化の重要性が喧伝された。作家や音楽家や俳優たちが、こぞって被災者のために何ができるのかと考えた。歌や音楽、心温まる小説や演劇、あるいは絵画やお笑いなどで、人々が勇気づけられ、活力を得ることもあっただろう。つまり、文化には素晴らしい力があるということだ。
しかし、すべての文化に素晴らしい力があるわけではない。むしろ、何の役にも立たない拙劣な自己満足も多いのではないか。
戦国時代、世の中が乱れて孤児があふれたとき、子どもたちが自らの生存をかけて「こどもの国」を創ったところから、水木マンガははじまる。
女の子たちがせっせと芋畑で働いていると、ねずみ男扮する腰巻デザイナーがやってきて、腰巻を売りつけようとする。女の子たちは芋を作るのに忙しく、それどころではないと断る。ねずみ男は「フランスの腰巻デザイナー、カルダン」と名乗り、桃色の腰巻を広げて誘惑する。女の子たちがそっぽを向くと、ねずみ男は軽蔑の視線で挑発する。
『あなた、美がわからないのネ』
それに対し、女の子たちが邪気のない澄んだ目で、冒頭の一言を返すのである。
空腹では、美も文化も役に立たない。崇高そうな理念や、意味不明な芸術性に目が眩んでいる文化人には、到底、発想し得ない真実だろう。
ねずみ男扮するカルダンは、貴族の奥方にデザインした腰巻が評価され、国王から勲章をもらったとうそぶく。すると、女の子はこう一蹴する。
『バカな国王ね。みちたりた人をたのしませたからって、なにも勲章まで……』
さらに平民の三太が登場し、ねずみ男を退散させようとして、冴えた一言を発する。
「貧乏人にものをほしがらせるのは商人のわるいくせだ」
これもまた、商人の本質を衝いている。テレビのCMを見ればわかることだ。
対して、ねずみ男は、『バカヤロウ。俺ア文化を向上させてやろうと思ってきたんだ』と反論する。たしかに文化の向上になるかもしれない。しかし、そのために空腹を満たすべき芋が、多量に商人にせしめられてもいいものだろうか。
文化は所詮、お遊びである。芸術に命を賭けた画家や小説家もいるだろうが、当人はともかく、それを普遍的な価値にされると、世間が迷惑する。
忘れがたい感動、熱い涙、身体の底から沸き上がる勇気と興奮もあるだろう。だが、それらはすべて衣食が足りての話だ。そこを勘ちがいすると、地から足が浮いてしまう。
マンガも堂々たる文化であることを考えれば、マンガで文化に冷水を浴びせる水木サンは、やはり見えていたとしか言いようがない。
(「こどもの国〈第一回〉大統領誕生」より)