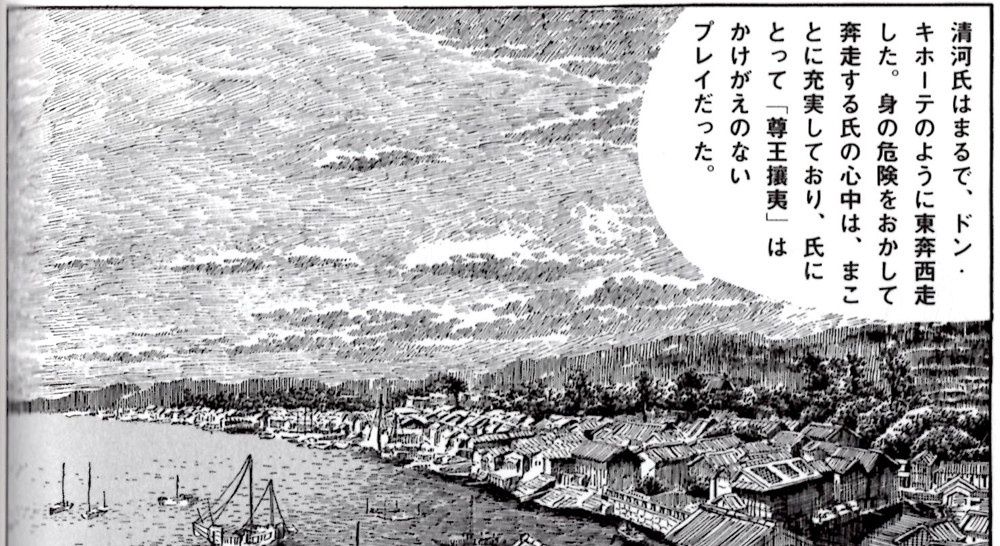【6】でも触れた近藤勇の一代記『星をつかみそこねる男』は、まさに「冴えてる一言」の宝庫である。とても1回では紹介しきれないので、しばらくお付き合いいただこう。
冒頭の一言は、新撰組結成のきっかけをつくった志士、清河八郎を紹介する一節である。
清河八郎(1830~1863)は庄内藩の出身で、北辰一刀流の免許皆伝、昌平黌にも学び、江戸に学問と剣術を指導する「清河塾」を開いた英才である。倒幕・尊皇攘夷を唱えて諸国を行脚し、京に潜伏したり、九州を遊説して薩摩藩に挙兵を勧めたりした。その後、今度は幕府に取り入り、江戸で浪士組を結成し、将軍上洛の前衛として京に上りながら、京に着いたとたん、真の目的は将軍警護でなく、尊王攘夷の先鋒となることであると言って、とんぼ返りに浪士たち連れて江戸にもどる。このとき、袂を分かって京に残ったのが、芹沢鴨、近藤勇、土方歳三ら、後に新撰組を結成するメンバーである。
清河は英才にはちがいないが、考えが極端というか、雄大すぎるというか、ひとりで国を背負って立とうとするかのような軽率さがあった。その状況を水木サンはこう説明する。
『清河氏はまるでドン・キホーテのように東奔西走した。身の危険をおかして奔走する氏の心中は、誠に充実しており……』
と説明されたあとに、冒頭の一言が語られる。
もちろん、清河自身は大まじめで、理想に燃えていたことだろう。私利私欲を捨て、大義を奉じ、己の信じる道を邁進しようとしたにちがいない。だが、その道は険しく、結局、策士の名をちょうだいしたあと、幕府ににらまれて暗殺される。
清河八郎の充実は、水木サンも書くように、困難であったり、危険であったりするほど高まった。それは清河の理想が、結局は彼自身の悦び、愉しみであったからだ。すなわち、“プレイ”なのである。
よく落選は確実なのに、選挙に打って出て、理想や気高い理念を語る人がいる。「だれもが笑顔になれる社会を」とか、「だれ1人見捨てない」とか、「貧困ゼロを目指して」など、現実には不可能だったり、財政や実務の裏付けを無視したスローガンを連呼する。これも“プレイ”なので、否定されたり、無視されたりすれば、それだけ快感とヤル気が増す。
テレビのコメンテーターやMCで、立派なことを言う人々も“プレイ”の要素が強い。慈善活動とか、反政府運動、デモや被害者の支援なども、善意の行動であるにはちがいないが、“プレイ”の一種だろう。善なる行動には、秘かな快感が潜んでいるのだから。
そんなふうに言うと怒る人もいるだろうが、それをしなければ生きていけない行動以外は、良きにつけ悪しきにつけ、すべて“プレイ”の範疇に入る。
『星をつかみそこねる男』では、ほかにも水木サンは冷厳な表現を駆使している。
たとえば、近藤勇が「日本外史」を読んで勉学に勤しんでいるとき、小間使いの小六に、こう説明する。
「これを読んでかしこくなって、将来、いい生活しようと思ってんだ」
何とも身も蓋もないセリフである。そんな近藤を見た土方歳三は、さらに追い打ちをけるように解説する。
「『尊皇攘夷』と一声さけんどかないと、いまの時代はかっこつかねえんだ」
皮肉な論評である。
現代も、叫んでおかなければ恰好がつかないセリフは多々ある。たとえば、「ハラスメント反対」とか、「イジメを許さない」とか。ほかにも「戦争反対」「核兵器反対」「差別反対」「人権尊重」「人命尊重」など、オーソドックスなものもある。いずれも重大で正しくはあるが、冷静に語る人は別として、まなじり決して叫ぶ人の心に、密かな快感は潜んでいないか。
自らの生活や命と引き替えにしても貫くというのなら、それは“プレイ”ではなく、“信念”である。しかし、自分を犠牲にしてまでそれを貫ける人が、どれだけいるだろう。
水木サンが辛辣な目を持ったのは、戦中戦後に、それまで立派なことを言っていた人が、手のひらを返したように浅ましい姿をさらしたり、戦場で命が紙キレのように軽く扱われたりする現実を、体験したからではないか。
極限状態を知る水木サンから見れば、理想も正義も真心も、“プレイ”の一種にすぎないのかもしれない。
(『星をつかみそこねる男』より)